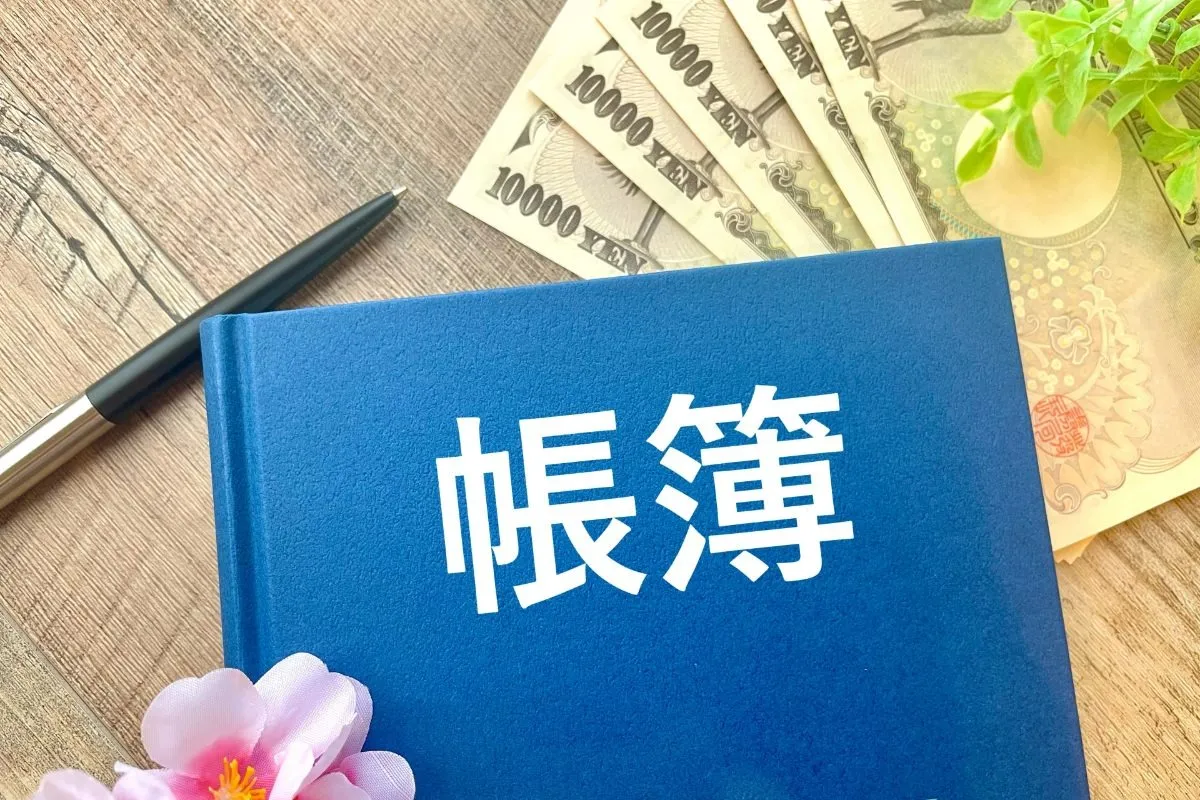法人の不動産売却に伴う費用仕訳を正しく整理する方法
不動産の売却を進める中で、登記費用や印紙税、仲介手数料などの「見落としがちな支出」に戸惑っていませんか。
「売却益が出たのに、なぜか手元に残る額が少ない」「この支払いってどうやって仕訳すればいいの?」そんな疑問を抱える法人の経理担当者や事業主は少なくありません。
正確な仕訳処理は、税務リスクを回避し、損失の未然防止にもつながります。読み進めれば、あなたの不安や迷いも数値と実務に基づく知識でクリアになるはずです。
株式会社トップトラストは、不動産の購入、管理、税務相談、売却など幅広いサービスをご提供しています。お客様のニーズに応じた最適な不動産プランをご提案し、安心・安全な取引をサポートいたします。また、経験豊富なスタッフが税務や法務に関するご相談にも対応し、お客様の大切な資産を守るためのアドバイスを行っています。不動産に関するあらゆるご要望にお応えし、お客様の夢を実現するお手伝いをいたします。

| 株式会社トップトラスト | |
|---|---|
| 住所 | 〒160-0007東京都新宿区荒木町5番地 四谷荒木町スクエア5F・6F |
| 電話 | 03-5315-0370 |
目次
不動産売却における法人の仕訳処理と税務対策
法人が不動産を売却する際の基本的な仕訳処理
法人が保有する不動産を売却する際には、会計上の仕訳処理が正確であることが極めて重要です。なぜなら、固定資産売却の処理は、帳簿価額や売却価額、取得時の減価償却費、さらに売却益や売却損といった複数の勘定科目が連動し、法人税や消費税の計算にも大きな影響を及ぼすからです。誤った仕訳は税務リスクや監査指摘の対象にもなり得るため、仕訳処理の精度は事業運営における信頼性を大きく左右します。
不動産を売却したときの会計処理の基本は、売却価額と帳簿価額の差額をもとに「固定資産売却益」または「固定資産売却損」を計上することです。帳簿価額とは、取得価額からこれまで計上された減価償却累計額を差し引いた残存価額を指し、この金額と実際の売却代金との間に差が生じれば、利益または損失として損益計算書に反映されます。
実際の仕訳例は以下のとおりです。
法人が建物を売却した際の基本的な仕訳(消費税課税対象の場合)
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 | 補足 |
| 普通預金 | 売却代金 | 建物 | 帳簿価額 | 取得価額から減価償却を差引 |
| 固定資産売却益 | 差額 | 利益が出た場合 | ||
| 仮受消費税 | 該当額 | 消費税課税の場合 |
建物売却の場合、原則として売上には消費税が課税されるため、売却代金には消費税が含まれます。土地については非課税資産のため、消費税の処理は不要です。したがって、複数の資産を同時に売却する場合は、土地と建物を按分して処理する必要があります。
加えて、売却時に仲介手数料や司法書士報酬などの経費が発生することも多く、これらは「支払手数料」または「租税公課」として別途仕訳を行い、法人税の計算に影響する費用項目として考慮されます。
仲介手数料の仕訳
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
| 支払手数料 | 該当額 | 普通預金 | 該当額 |
売却によって得られる資金が「現金」ではなく「売掛金」や「未収入金」として処理されるケースもあります。売却契約から決済日までにタイムラグがある場合、売却時点では「未収入金」で記録し、入金時に「普通預金」へと振替します。
このように、固定資産の売却には単純な収支の記録だけでなく、取引の内容・タイミング・金額・税務上の課税区分を的確に反映させることが求められます。特に期中の売却であれば、減価償却の按分計算や、決算日との整合性をとった処理が必須です。
不動産を売却する法人は、取引の性質を深く理解し、帳簿価額や償却計算をもとに適正な仕訳を組み立てるスキルが求められます。これらの理解が不十分なまま会計処理を行うと、不要な税金負担や誤認による追徴課税のリスクがあるため、専門家と連携しながら正確な会計処理を徹底することが重要です。
不動産売却益と売却損の計上方法
法人が不動産を売却した場合、売却価額と帳簿価額の差額によって「売却益」または「売却損」が発生します。これらの損益は、企業の収益や費用に直結し、法人税額や財務諸表に影響を与えるため、正確な処理が求められます。
売却益の計上は以下の条件で発生します。
- 実際の売却価格が帳簿価額を上回る場合
- 減価償却済みの金額が大きく、資産価値がほとんど残っていない場合
- 不動産市況の上昇などにより高値での売却が成立した場合
売却損は以下のようなケースで発生します。
- 売却価格が帳簿価額を下回った場合
- 市場価値が著しく低下していた資産を処分した場合
- 長期保有によって建物が老朽化していた場合
売却益・売却損の仕訳比較
| 売却状況 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 売却益発生時 | 普通預金 | 売却代金 | 固定資産(例 建物) | 帳簿価額 |
| 固定資産売却益 | 差額 | |||
| 売却損発生時 | 普通預金 | 売却代金 | 固定資産(例 建物) | 帳簿価額 |
| 固定資産売却損 | 差額 |
この仕訳の処理においては、譲渡所得や消費税の課税有無も大きく関係します。土地は非課税、建物は課税対象のため、売却益が出た場合は売上として「仮受消費税」の仕訳も追加する必要があります。売却損が出た場合でも、会計上は損失として計上されるものの、税務上は一部損金不算入となる場合があるため、法人税の計算と仕訳には注意が必要です。
売却損益は、法人の決算において重要なポイントであり、決算前のタイミングで売却を行う場合は、帳簿価額の再評価や税務戦略の見直しも求められます。建物の減価償却費を見直すことで、売却損益の調整が可能になる場合があります。
減価償却の計算方法には「定額法」や「定率法」などがあり、適用される方法により帳簿価額の変動が異なるため、どの方式を用いているかの確認も不可欠です。2025年現在の会計基準においては、固定資産の除却損・廃棄損などと売却損を明確に区別して記録することが求められており、会計システムや弥生会計などの処理方法においても設定ミスがないよう注意が必要です。
これらの仕訳処理は、業種や不動産の種類(例えば事業用建物か投資用マンションか)によっても若干異なるため、法人の業態に応じてカスタマイズすることが望ましいです。とくに不動産業や建設業を営む法人の場合、販売用不動産と固定資産との違いによって処理が分かれるため、注意が必要です。
このように、売却益と売却損の計上方法は単純な利益の反映にとどまらず、税務申告・決算報告・法人税計算に直結する重要な処理項目です。経営判断や税務戦略の一環として、正確かつ最適な処理が求められる領域です。会計士や税理士と連携しながら、自社の経営方針に合った形で売却処理を行うことが、企業価値の維持と健全な財務体質づくりに貢献します。
法人の不動産売却における消費税の取り扱いと仕訳
建物売却時の消費税処理と仕訳
法人が保有する建物を売却する際、その取引は原則として課税対象となります。これは建物が有形の固定資産であり、事業活動の一環として譲渡されるため、消費税法上の課税売上に該当するためです。売却益が発生するか否かにかかわらず、売却金額に対する消費税の適切な会計処理が求められます。
建物売却における会計処理の基本構造は、以下の通りです。
- 固定資産売却による収益の計上
- 帳簿価額(簿価)および減価償却累計額の消去
- 消費税の仮受消費税の認識
- 売却益または売却損の計上
帳簿上の建物価格が取得価額から減価償却を差し引いた残存簿価であり、売却金額がこれを上回る場合は「固定資産売却益」として収益認識されます。逆に下回れば「固定資産売却損」として費用処理されます。消費税は売却価額のうちの消費税相当額を「仮受消費税」として処理し、課税売上に対応した控除対象仕入税額と相殺されます。
以下のテーブルは建物売却における一般的な仕訳例を整理したものです。
建物売却時の仕訳例(課税対象取引)
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
| 現金(普通預金) | 売却価額 | 建物 | 取得原価 |
| 減価償却累計額 | 償却済額 | 固定資産売却益 or 売却損 | 差額 |
| 仮受消費税 | 消費税額 |
このように、売却時には建物の帳簿価額(取得原価-減価償却累計額)を正確に把握し、それと売却価額との差額を利益もしくは損失として適切に処理します。売却価額に含まれる消費税額は「仮受消費税」勘定として記帳され、消費税申告時の税額控除に用いられます。
注意点として、売却に際しては仲介手数料や司法書士報酬といった付随費用が発生することがあります。これらは「支払手数料」や「租税公課」などの勘定科目で処理され、必要に応じて消費税の仕入税額控除の対象にもなります。
事業用建物の売却であるかどうかも重要な判断基準となります。自社利用の社屋や倉庫など、事業活動で使用されていた建物であれば課税対象ですが、例えば福利厚生施設など非課税事業に用いられたものの場合、仕訳処理や消費税の扱いが異なるケースもあるため注意が必要です。
インボイス制度下においては、売却先が適格請求書発行事業者であるか、適格インボイスを発行しているかがポイントになります。インボイスの発行がなければ、買主側が仕入税額控除を受けられないため、取引自体が不利になることもあります。売主としても、制度への正しい理解と対応が求められます。
このように、建物の売却には単なる会計処理だけでなく、税務・制度面での対応が不可欠です。特に中小企業や不動産管理法人では、インボイス登録や課税事業者の選択、適正な仕訳処理を誤ると、税務調査の際に指摘を受けるリスクもあります。税理士などの専門家に相談しながら進めることで、トラブル回避と節税の両立が可能になります。
土地売却は消費税非課税(処理時の注意点)
土地の売却は、消費税法上「非課税取引」とされています。これは、土地という資産が「消費される財・サービスではない」とされており、税の公平性と制度趣旨に基づいているからです。よって、法人が土地を売却する場合、その取引に対して消費税は課税されません。
非課税であるとはいえ、仕訳処理を簡略に扱ってしまうと、誤った会計処理につながる恐れがあるため注意が必要です。土地の売却時には、取得原価と簿価の差額によって売却益または売却損が発生し、これを正確に会計上に反映させる必要があります。
以下は、土地売却における一般的な仕訳例です。
土地売却時の仕訳例(非課税取引)
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
| 現金(普通預金) | 売却価額 | 土地 | 取得原価 |
| 固定資産売却益 or 売却損 | 差額 |
ここで大切なのは、売却価額に消費税は含まれないため、「仮受消費税」などの勘定科目は登場しない点です。その分、インボイス制度下においては土地の売却にインボイスの発行義務はありません。これは売主・買主ともに共通の理解が必要です。
ただし、土地の売却に付随して建物が同時に売却されるケースでは、建物部分についてのみ課税取引として消費税が発生します。このような「一括売却」の場合、土地と建物の按分計算を適切に行い、それぞれに対応した課税・非課税仕訳を行う必要があります。国税庁の通達では、合理的な基準(契約書記載、登記簿面積など)に基づく按分が求められており、実務では「土地と建物の比率算出」が必須となります。
以下のような注意点も押さえておくと、処理ミスを防げます。
土地売却処理における注意点
- 減価償却は行わない(建物と異なり土地は非償却資産)
- 仲介手数料や登記費用は「支払手数料」や「租税公課」として処理
- 固定資産税精算金は「租税公課」または「雑収入」で処理可能
- 取得費に不動産取得税や登録免許税を含めるかの判断は税理士と要相談
- 消費税区分の誤記載による経理ミスは、税務調査での指摘対象となる
法人税や地方税の計算においても、売却益が課税所得に加算される点や、損失が出た場合の繰越控除の可否といった論点も存在します。帳簿上の処理だけでなく、税務的な視点も踏まえて対応する必要があります。
近年では電子帳簿保存法やインボイス制度への対応も求められており、帳簿の電子保存や取引記録の適正な管理も重要です。税務リスクを最小限にするためには、法改正の動向に注意し、会計ソフトのアップデートや専門家との連携も検討すべきです。
土地の売却は消費税がかからないからといって気を抜くことなく、仕訳処理・按分・帳簿の整合性・インボイス制度への対応など、多方面にわたる注意が求められる取引です。特に建物との一括取引となる場合には、課税・非課税の混在処理が発生するため、実務に即した丁寧な対応が成功の鍵を握ります。
法人税・地方税と不動産売却益の関係
売却益が法人税に与える影響とは?
法人が不動産を売却する際に得られる売却益は、法人税の課税所得に直接的な影響を与える重要な要素です。会計上の損益計算とは異なり、法人税法上の課税対象は「益金から損金を差し引いた所得」であるため、不動産売却益の扱いは法人の税務申告において極めて重要です。
不動産売却による利益は、帳簿価額(簿価)と売却価額との差額として計算され、会計上では「固定資産売却益」または「特別利益」として計上されます。そしてこの利益は、税務上では法人税課税所得に含まれ、他の収益と合算して申告されます。
下記の表では、不動産売却に関わる主な税務会計処理の流れと影響をまとめています。
| 区分 | 会計上の処理 | 税務申告上の処理 | 備考 |
| 売却益 | 固定資産売却益(益金) | 課税所得に含まれる | 売却価額-帳簿価額 |
| 減価償却累計額 | 売却時点で固定資産から除却 | 簿価計算に影響 | 売却益計算に必要 |
| 仲介手数料 | 販売費および一般管理費 | 損金算入可 | 売却と同時に経費処理 |
| 固定資産税精算額 | 支払時に租税公課として処理 | 原則損金算入可 | 買主との按分に注意 |
特に誤解されやすいのが、「不動産売却益=すべてが法人税対象になる」との認識です。実際には、売却に際してかかった仲介手数料や登記費用などの支出は、損金として益金から差し引くことができるため、正しい経費処理が重要となります。適正な減価償却費を計上していないと帳簿価額がずれ、結果的に過大な売却益が計上されるリスクもあるため注意が必要です。
法人税申告書においては、別表五(一)などで固定資産の異動を明示し、売却益の発生に伴う「税務調整」を行う必要があります。たとえば、会計上で売却益を計上していても、税務上は償却超過部分などの調整が必要になることもあります。
- 売却益の金額はどう計算されるか?
- 仲介手数料などの諸費用は損金になるのか?
- 期中に売却した場合の減価償却はどのように処理するのか?
- 決算期直前に売却した場合、税金は翌期になるのか?
- 売却益が大きく出た場合の節税対策にはどのような方法があるのか?
こうした疑問に応えるには、会計処理だけでなく税務申告書の記載方法や法人税計算に用いられる具体的な調整項目への理解が不可欠です。
なお、法人税法では「益金」として売却益を定義し、これに対応する「損金」項目として費用や減価償却費を認めています。したがって、売却益が発生したとしても、適切な損金算入処理によって実効税率の軽減は可能です。
中小企業にとっては事業用不動産の売却益が一時的に大きな課税所得となり、キャッシュフローに影響を与えるケースも少なくありません。節税の観点からは、期ズレを避けるための売却タイミングや、売却に伴う費用の確実な計上が重要となります。
このように、法人が不動産を売却する際の売却益の取り扱いは、単なる「利益の増加」ではなく、法人税の実質的な課税負担を決定づける要因であり、制度的な理解と専門的な対応が欠かせません。適切な処理と正確な申告が、企業経営における納税コストの最適化につながります。
売却に伴う地方税(住民税・事業税)の負担
不動産の売却により法人が得た利益は、法人税の課税対象となるだけでなく、地方税である法人住民税および法人事業税の負担にも直結します。多くの法人担当者が見落としがちなのが、これら地方税が単独で課税されるのではなく、「法人税の課税所得」や「法人税額」を基準に計算されるという点です。この関係性を正しく理解しておくことで、決算時や売却前後の資金繰りにも有効な見通しを立てられるようになります。
まず法人住民税について説明します。法人住民税は、都道府県民税および市区町村民税の総称で、法人の所在地によって課される地方税です。課税方法は2つの要素に分かれます。1つは法人税額に比例する「法人税割」、もう1つは所得の有無にかかわらず定額で課される「均等割」です。特に法人税割は、不動産の売却益により法人税額が増加すると、それに連動して自動的に増えるため、結果として法人住民税の負担も増加します。つまり、不動産売却によって一時的に大きな利益が計上された場合、法人税だけでなく住民税も連動して上昇するという構造です。
法人事業税も同様に、所得に基づいて課税される仕組みです。法人事業税は法人の「所得割課税方式」に基づいて計算されるもので、課税所得が大きくなることで税額が増加します。ここでの「所得」は、法人税の計算ベースと一致するため、不動産売却により得た益がある場合、その全体が事業税の算定対象に含まれます。ただし、課税所得には一定の調整項目があるため、売却益の全額がそのまま反映されるわけではない点に注意が必要です。
法人事業税のもう一つの特徴は、外形標準課税の適用対象となる場合があることです。外形標準課税は、資本金や従業者数などの規模によって一部法人に対して適用され、資本金が一定以上でかつ従業員数が多い企業には、所得だけでなく「付加価値割」「資本割」といった形での課税が追加されることがあります。不動産売却自体がこの課税方式の変更要因となることは少ないですが、事業の拡大とともに制度の適用対象となる可能性もあるため、注意が必要です。
各地方自治体における法人住民税および事業税の税率には、ある程度の幅が存在します。同じ課税所得でも、東京都に本店を置く法人と、地方の中小都市に所在する法人では、税負担に差が出るケースがあります。これは、自治体ごとの法人税割率や事業税率が異なるためです。売却益の発生が見込まれる法人は、所在地の税率体系を確認しておくことが不可欠です。とりわけ、移転やグループ会社間の資産移動を伴うような戦略的売却を検討している場合、税率の違いによる費用差を意識した事前検討が重要となります。
法人税と連動して発生する地方税の概要を整理したものです。
法人地方税の概要比較
| 税目 | 課税根拠 | 課税内容 | 税率の影響 | 主な注意点 |
| 法人住民税 | 法人税額に比例 | 法人税割+均等割 | 高い | 所在地によって税率が異なる |
| 法人事業税 | 所得金額に基づく | 所得割(+外形標準課税の場合あり) | 中程度 | 資本金や従業員数に応じ課税変動あり |
このように、不動産売却益が発生すると、その利益の性質や税務上の位置づけに応じて地方税の負担が加算されていきます。法人税・住民税・事業税はいずれも「法人税等」として連携した仕組みで課税されるため、単独で対策を講じるのではなく、3税一体で考えることが重要です。加えて、特別償却や繰越欠損金の活用、グループ法人税制への対応など、各種控除や節税策を活用することで、課税所得および課税額の調整が可能となります。
税額を正確に把握するためには、決算期前に仮決算を行い、想定される不動産売却益および地方税の増加額を見積もっておくことが賢明です。これにより、資金繰りの悪化や納税資金不足といったリスクを事前に回避できます。インボイス制度導入後は、地方税の根拠資料となる帳簿や仕訳の精度が、税務調査時の信頼性にも関わってきます。
売却時に発生するその他費用の仕訳
登録免許税・印紙税・司法書士報酬などの処理
不動産売却に際しては、単に売却代金の受領や固定資産の除却処理を行うだけでなく、法的・実務的なコストが必ず発生します。これらの費用は会計処理や税務申告において重要な項目となり、それぞれの性質を理解したうえで仕訳処理を行う必要があります。具体的には、登録免許税・印紙税・司法書士報酬・登記関係諸費用などが該当します。
まず登録免許税は、不動産の名義変更登記を行う際に課される税金であり、税法上「租税公課」として分類されます。実際の支払いは金融機関や司法書士を通じて行うことが多く、その場合の仕訳では借方に「租税公課」、貸方に「普通預金」または「現金」を計上します。非課税扱いである点が特徴です。登記の内容によって税率が異なるため、取得登記と保存登記、変更登記の区別をしっかり行い、実務上のミスを防ぐ必要があります。
続いて印紙税は、不動産売買契約書に添付する印紙に係る税金で、これも「租税公課」として処理します。課税対象外であることに加え、契約書の記載金額に応じて印紙の額面が変動するため、契約時に税額表で確認することが求められます。売買金額が大きくなればなるほど、印紙税の負担も比例して増加する点に注意しましょう。仕訳では、支払時に「租税公課」を借方、「現金」または「預金」を貸方とするのが基本です。
司法書士報酬については、登記手続きを代行する専門職に対する業務報酬として支払われます。これには消費税が課税されるため、仕訳上は「支払手数料」として処理され、インボイス制度への対応も必要です。仕訳は、借方に「支払手数料」、貸方に「普通預金」または「現金」となります。この処理においては、請求書の保存と消費税額の明示が求められ、消費税の控除対象にもなり得るため、税務署の監査対応にも関わる重要なポイントとなります。
仲介手数料・管理費清算・広告費の仕訳処理
不動産の売却に際して発生する費用の中で、最も実務処理が複雑になりやすいのが「仲介手数料」「管理費清算」「広告費」です。これらは法的義務ではないものの、売却活動に欠かせない業務経費であり、適切な会計処理が求められます。特に勘定科目の選定、消費税区分、発生タイミングに応じた処理は税務上の正確性に直結します。
以下に、それぞれの項目ごとの勘定科目分類・消費税区分・仕訳例を明確にしたテーブルを提示します。
売却に関連する実務費用の仕訳一覧表
| 費用項目 | 勘定科目 | 消費税区分 | 仕訳処理例(借方) | 仕訳処理例(貸方) | 留意点 |
| 仲介手数料 | 支払手数料 | 課税対象 | 支払手数料(消費税含) | 普通預金または未払金 | インボイス発行の有無を確認、原則課税対象 |
| 管理費の精算 | 租税公課/未収入金 | 非課税 | 未収入金または租税公課 | 現金/預金/売掛金 | 売買契約時に按分計上。実費の場合は清算書添付要 |
| 修繕積立金等 | 雑費/租税公課 | 非課税 | 雑費または租税公課 | 現金または普通預金 | 管理組合等の証憑に基づき実費を仕訳する |
| 広告費 | 広告宣伝費 | 課税対象 | 広告宣伝費(消費税含) | 普通預金または現金 | 契約書や見積書を保存、仕訳時期にも留意 |
このように、実務に即した仕訳処理を行うことで、法人税や消費税の申告時の整合性が保たれ、トラブルを未然に防ぐことが可能になります。以下のような具体的な実務上の注意点があります。
実務上の注意点リスト
- 契約タイミングの一致確認
- 仲介手数料や広告費は「契約締結時」「売却完了時」など、いつ費用認識するかで処理が異なるため、契約書・領収書の発行日を確認し、発生主義に基づいて処理する必要があります。
- 課税対象と非課税の見極め
- 仲介手数料・広告費は課税対象であるため、インボイス制度下では適格請求書の有無が控除可否に影響します。
- 管理費や修繕積立金は非課税扱いが多く、仕訳科目の選定を間違えると消費税の計算が狂います。
- 支出負担者と負担区分の明確化
- 「管理費の未払い分を売主が負担」「修繕積立金は清算不要」などの合意がある場合、清算書に従った調整仕訳を行い、未収金や未払金で対応します。
- 広告費の内容と分類
- 折込チラシ・ネット掲載・動画制作など、内容によっては「販売促進費」や「委託費」に分類されることもあります。具体性に応じた科目選定が求められます。
課税・非課税の判定まとめ表(インボイス制度対応)
| 費用種別 | 課税区分 | インボイス必要性 | 消費税処理の注意点 |
| 仲介手数料 | 課税対象 | 必要(要適格請求書) | 控除可能な仕入税額に該当、請求書の保存要件あり |
| 広告費 | 課税対象 | 必要(要適格請求書) | 掲載内容や業者により分類が変わることに留意 |
| 管理費精算 | 非課税 | 不要 | 売主負担か買主負担かで処理が異なる |
| 修繕積立金等 | 非課税 | 不要 | 実費負担の有無で、売買契約上の清算有無を確認 |
これらを正確に処理することで、法人税・消費税ともに適切な申告が可能になり、税務リスクの回避に大きく貢献します。特に仕訳記録時には、関連資料(契約書・清算書・請求書)の保管と勘定科目の正確性が重要です。
まとめ
不動産の売却に際して発生する費用や仕訳処理は、多くの法人担当者にとって見落としやすい部分です。登録免許税や印紙税、司法書士への報酬などの法的手続き費用はもちろん、仲介手数料や管理費の精算、広告費といった実務的な支出も、正確な処理が求められます。これらを適切に会計帳簿へ反映させることで、法人税や地方税の算定にも大きな影響を与えるため、損益のズレや税務リスクを回避するうえでも重要です。
仕訳処理の際には、経費の発生タイミングや支払いの実態、相手方との契約内容など、実務に即した判断が不可欠です。仕訳に用いる勘定科目の選定を誤ると、経費性の否認や修正申告が必要となるケースもあります。
費用区分ごとの仕訳方法に加え、実際の税務処理に直結する損益の算定や課税所得への反映までを明確に整理しました。帳簿処理を正確に行うことは、法人としての信用力を高めると同時に、将来の税務調査に対する備えにもなります。
不動産売却の仕訳を軽視すれば、後のトラブルやコストの増加につながりかねません。だからこそ、今のうちに正しい知識を身につけ、実務で活用できるレベルにまで落とし込んでおくことが不可欠です。損失を回避し、経営資源を最大限に活かすための一歩として、この記事の内容を実践に取り入れてみてください。
株式会社トップトラストは、不動産の購入、管理、税務相談、売却など幅広いサービスをご提供しています。お客様のニーズに応じた最適な不動産プランをご提案し、安心・安全な取引をサポートいたします。また、経験豊富なスタッフが税務や法務に関するご相談にも対応し、お客様の大切な資産を守るためのアドバイスを行っています。不動産に関するあらゆるご要望にお応えし、お客様の夢を実現するお手伝いをいたします。

| 株式会社トップトラスト | |
|---|---|
| 住所 | 〒160-0007東京都新宿区荒木町5番地 四谷荒木町スクエア5F・6F |
| 電話 | 03-5315-0370 |
よくある質問
Q. 不動産を法人で売却する場合、仲介手数料や司法書士報酬の仕訳はどうなりますか?
A. 不動産売却に伴う仲介手数料は「支払手数料」、司法書士報酬は「租税公課」や「支払手数料」で処理するのが一般的です。たとえば仲介手数料として支払った費用は、消費税の課税対象となる場合があり、帳簿に正しく記載しないと税務リスクを招くおそれがあります。特に司法書士の登記報酬に含まれる登録免許税などは非課税項目となるため、明細に応じた会計処理が必要です。
Q. 売却益が出た場合、法人税だけでなく地方税にも課税されるのですか?
A. はい、法人が不動産を売却して利益が出た場合、その利益は「課税所得」として法人税の対象になるだけでなく、法人住民税および事業税にも影響します。法人住民税は均等割と法人税割から構成され、利益額によっては地方税の負担も大きくなります。事業税の税率や計算方法は都道府県ごとに異なり、適切な処理を行わないと、決算時に想定外の支出が生じるケースもあります。
Q. 管理費の精算や広告費は、どのタイミングで仕訳すればよいですか?
A. 管理費精算は引き渡し日を基準に「未払費用」または「前払費用」として調整します。広告費については、掲載媒体や掲載日によって「支払手数料」や「販売促進費」として計上するのが一般的です。売却のために実施した広告が決算期をまたぐ場合、発生主義で処理する必要があるため、処理タイミングには細心の注意が求められます。正確な日付や領収書の保管も重要で、税務調査時に帳簿と証拠の整合性が問われます。
会社概要
会社名・・・株式会社トップトラスト
所在地・・・〒160-0007 東京都新宿区荒木町5番地四谷荒木町スクエア5F・6F
電話番号・・・03-5315-0370