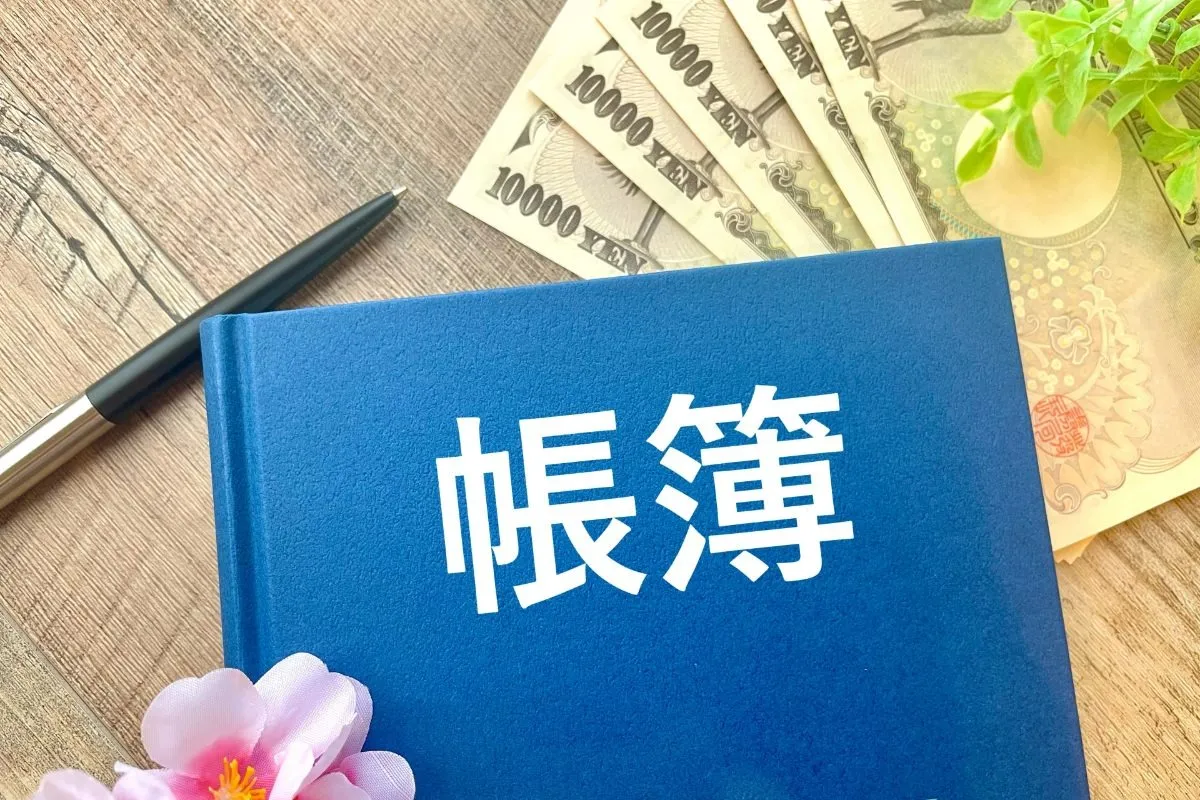相続の不動産売却における確定申告は不要?
「相続した不動産を売却したけれど、確定申告って必ず必要なの?」
そんな疑問や不安を抱えていませんか?
特に「申告しなくても大丈夫なケース」や「税務署に指摘されるリスク」を正しく把握していないと、知らぬ間に延滞税や無申告加算税の対象になる恐れもあります。実際、国税庁が公開するデータによれば、不動産売却に関する誤った申告や無申告によるペナルティの指摘件数は毎年数万件に上ります。
さらに、相続による不動産売却では、ケースによっては確定申告が不要になることもあるため、必要書類や譲渡所得の有無、控除の適用可否といった判断材料を整理しておくことが極めて重要です。
「書類が足りないときはどうすればいいの?」「税務署はどこまでチェックしているの?」といった疑問にも、現場での実務に基づいた視点で徹底解説します。
本記事では、「確定申告が不要になる代表的な条件と判断のポイント」を網羅的に紹介しています。
損失回避のためにも、知らずに損をする前に、ぜひ最後までお読みください。
株式会社トップトラストは、不動産の購入、管理、税務相談、売却など幅広いサービスをご提供しています。お客様のニーズに応じた最適な不動産プランをご提案し、安心・安全な取引をサポートいたします。また、経験豊富なスタッフが税務や法務に関するご相談にも対応し、お客様の大切な資産を守るためのアドバイスを行っています。不動産に関するあらゆるご要望にお応えし、お客様の夢を実現するお手伝いをいたします。

| 株式会社トップトラスト | |
|---|---|
| 住所 | 〒160-0007東京都新宿区荒木町5番地 四谷荒木町スクエア5F・6F |
| 電話 | 03-5315-0370 |
目次
相続不動産売却と確定申告の基礎知識
相続と譲渡所得の基本構造を理解する
相続で取得した不動産を売却する場合、その利益には「譲渡所得税」が関係してきます。譲渡所得とは、不動産などの資産を売却したときに発生する所得のことで、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた金額が該当します。相続においては、被相続人が保有していた資産を相続人が受け継ぎ、それを売却するという流れになるため、通常の売却とは取得のタイミングや課税の対象が異なります。
特に注意すべきは、譲渡所得の計算方法です。取得費が不明な場合、実際の支出を証明できなければ、国税庁が定めた概算取得費(売却価格の5パーセント)で計算する必要があります。これは実際の取得費が高い場合には不利に働く可能性があり、課税額が増える要因になります。
また、売却による利益が出なかった場合、すなわち譲渡損失が出た場合でも確定申告の義務が免除されるケースがありますが、それには明確な基準があります。たとえば、譲渡所得がマイナスであっても他の所得と合算して申告義務が発生する場合や、損益通算や繰越控除を希望する場合は申告が必要になります。
不動産の売却益は「譲渡所得」として申告されますが、給与や年金などの「総合課税」対象とは異なり「分離課税」として扱われ、税率も異なります。所有期間によっても課税方法が変わり、短期所有(5年以下)なら税率が高く、長期所有(5年超)なら軽減税率が適用される仕組みです。相続による取得は「被相続人が保有していた期間」を引き継げるため、実際には長期譲渡所得となるケースがほとんどです。
譲渡所得の計算式は次のとおりです。
譲渡所得の基本計算式
| 計算項目 | 内容 |
| 売却価格 | 不動産の売買契約に基づいた金額 |
| 取得費 | 被相続人が不動産を取得した際の価格や諸経費(登記費用、仲介手数料など) |
| 譲渡費用 | 売却にかかった費用(仲介手数料、測量費、解体費など) |
| 譲渡所得 | 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用) |
この譲渡所得に対して、所得税および住民税が課税されます。また、復興特別所得税も追加で発生するため、税額はやや複雑になります。
不動産の売却タイミングや取得費の取り扱いは、確定申告の有無や税負担に大きく影響を与えるため、事前にしっかりと理解しておく必要があります。特に「相続した不動産はいつ取得したとみなされるか」「どこまでが譲渡費用として認められるか」といった細かな判断は、国税庁のガイドラインや専門家の知見を参考にしながら進めることが求められます。
相続税と所得税の違いを正しく知る
相続した不動産を売却する際には、「相続税」と「譲渡所得税(所得税)」という2種類の税金が関係してきます。この2つの税は性質も納税義務もまったく異なるため、混同しないことが非常に重要です。
相続税は、被相続人が亡くなった際に、その遺産を受け取る相続人に課される税金です。相続時点の資産評価額(不動産・現金・株式などの合計額)から基礎控除を引いた額に対して課税されます。相続税は相続が発生してから10か月以内に申告・納税する必要があり、申告先は税務署です。
一方、所得税(この場合の譲渡所得税)は、相続した不動産を売却して得られた利益に対して課される税金です。売却の年の翌年に確定申告し、譲渡所得に応じて納税します。つまり、相続税と所得税は「課税タイミング」「課税対象」「申告方法」「納税時期」がすべて異なります。
このように両者を混同すると、不要な税負担が発生したり、期限内に申告しなかったことで延滞税や無申告加算税などのペナルティが発生するリスクがあります。
実際の比較を以下にまとめます。
相続税と所得税(譲渡所得税)の違い
| 項目 | 相続税 | 所得税(譲渡所得税) |
| 課税の対象 | 被相続人から受け継いだ全財産 | 売却によって発生した利益(譲渡所得) |
| 申告・納税時期 | 相続開始(死亡)から10か月以内 | 売却のあった年の翌年3月15日まで |
| 課税主体 | 相続人全員 | 売却した相続人(単独または共有者) |
| 管轄機関 | 被相続人の住所地の税務署 | 売却した人の住所地の税務署 |
| 控除や特例 | 基礎控除、配偶者控除、小規模宅地等の特例など | 取得費加算の特例、3000万円特別控除、長期譲渡控除など |
たとえば、相続税を支払った不動産を売却した場合、その相続税の一部を取得費に加算できる「取得費加算の特例」があります。この制度を使えば、課税される譲渡所得を減らし、結果的に納税額を軽減できる可能性があります。
ただし、この特例は相続発生から3年以内の年末までに売却した場合に限られるため、売却のタイミングによっては適用できないこともある点に注意が必要です。
確定申告の義務が発生する3つのパターン
相続した不動産を売却した場合、必ずしも確定申告が必要になるとは限りません。ただし、以下の3つの代表的なケースでは、確定申告の義務が発生します。
- 売却によって譲渡所得が発生した場合
- 3000万円特別控除などの特例を適用する場合
- 譲渡損失の繰越控除や損益通算を行う場合
まず、売却によって利益(譲渡所得)が出た場合は、その金額が20万円を超えていれば申告が必須です。これは他の所得と合算されて課税されるわけではなく、分離課税で扱われますが、確定申告は必要となります。
次に、譲渡所得が控除や特例によってゼロになる、あるいは赤字になる場合でも、「3000万円特別控除」「取得費加算の特例」「空き家譲渡の特例」などの税制優遇措置を受けたい場合には、確定申告をしておかなければ特例が適用されません。
さらに、譲渡損失が出た場合でも、給与所得など他の所得と通算して課税額を減らす「損益通算」や、翌年以降に損失を繰り越して控除できる「繰越控除」を利用するには、やはり確定申告が必要です。
また、以下のようなケースも注意が必要です。
・取得費が不明で概算取得費を使うため、譲渡所得が過大に見積もられる場合
・土地の評価額と実売却額に乖離がある場合
・複数人の共有名義で売却した場合
これらのパターンでは、税務署に対して正確な情報を伝えるためにも、確定申告を行っておく方がトラブル回避につながります。
相続不動産の売却による確定申告が不要と判断できるのは、譲渡所得がゼロまたはマイナスで、特例や控除の申請も一切行わない場合に限られます。ただし、それでも「不要」と断言するには慎重な判断が求められ、最終的には税務署や専門家への確認が安心です。特に近年は税務署の確認体制も強化されており、後日追徴課税される例も増えています。
したがって、税務リスクを避けるためにも、自分がどのパターンに該当するのかを明確にしたうえで、確定申告の要否を検討することが大切です。
相続不動産の売却で確定申告が「不要」な主なケース
譲渡所得がマイナスである場合
相続した不動産を売却した際、その売却によって利益が出なかった、つまり譲渡所得がマイナスだった場合には、原則として確定申告が不要になることがあります。譲渡所得とは、売却価格から取得費や譲渡費用などを差し引いた金額です。これがマイナスである場合、課税対象となる所得がないため、課税義務も発生しません。
ただし、「確定申告が本当に不要か」を判断するには、まず譲渡所得の計算が正確にできている必要があります。ここで重要になるのが取得費の設定方法です。相続によって不動産を取得した場合、被相続人が購入した時点の取得費を引き継ぐことになります。仮に取得費が不明な場合は、概算取得費として売却価格の5パーセントで計算されるため、結果として譲渡所得が大きくなり、マイナスではなくプラスになる可能性もあります。
譲渡所得の計算式は次のとおりです。
譲渡所得の計算式
| 計算項目 | 内容 |
| 売却価格 | 実際の不動産売買契約における金額 |
| 取得費 | 被相続人が不動産を購入した金額+取得時の諸費用(登記費用、仲介手数料など) |
| 譲渡費用 | 売却にかかった経費(仲介手数料、測量費、建物解体費用など) |
| 譲渡所得 | 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用) |
たとえば、以下のようなケースです。
- 売却価格が2000万円
- 取得費が2500万円(被相続人が購入時に支払った価格+諸費用)
- 譲渡費用が100万円
この場合、譲渡所得はマイナス600万円となり、課税対象がなくなるため、確定申告が不要になる可能性があります。
ただし、譲渡所得がマイナスでも「損益通算」や「繰越控除」を希望する場合には、確定申告を行う必要があります。損益通算とは、他の所得(給与や年金など)と合算して税負担を減らす制度であり、繰越控除は損失分を翌年以降に繰り越して控除できる制度です。これらの制度を使うには確定申告が必須であり、「不要」と判断して放置すると節税機会を失うリスクがあります。
また、売却にかかった費用や取得費の妥当性は、税務署から確認される場合があります。特に、不動産の取得時期が古く、領収書や契約書が残っていないケースでは、費用が証明できずに概算で処理せざるを得ないため、注意が必要です。
相続不動産の売却における確定申告の要否は、譲渡所得の内容だけでなく、他の控除制度の活用意向や書類の有無など複数の要因によって変わるため、単に「マイナスだったから不要」と安易に判断せず、慎重に計算・検討することが求められます。
譲渡所得と他の所得の合計が20万円以下の場合
譲渡所得が発生したとしても、その金額と他の所得の合計が年間20万円以下であれば、確定申告が不要となる場合があります。これは所得税法における「20万円基準」の特例によるもので、主に副業や臨時収入などが該当しますが、不動産の譲渡所得もこの対象に含まれることがあります。
ただし、この特例はすべての人に適用されるわけではありません。具体的には以下の条件を満たす必要があります。
- 給与所得者であること(年末調整済みのサラリーマンなど)
- 給与以外の所得(譲渡所得など)が年間20万円以下
- 住民税の申告義務が別途ないこと
このため、たとえ譲渡所得が20万円以下でも、住民税の観点では申告が必要なケースがあります。多くの自治体では、住民税の申告をしていないと正確な課税ができないため、結果として「住民税の申告だけ必要」という事態も想定されます。
また、譲渡所得が20万円以下であっても、以下のような例外があります。
・特別控除(3000万円控除など)を適用したい場合 ・取得費加算の特例を活用したい場合 ・複数の不動産を同一年内に売却している場合 ・扶養控除や配偶者控除の条件に影響を与える場合
これらに該当するケースでは、確定申告を行うことで節税効果が得られる可能性があり、「申告しなくてもいいからしない」ではなく、「あえて申告する価値があるか」を検討すべきです。
また、税務署の立場では、所得が20万円以下であっても「取引の内容が不明確」「取得費の証明があいまい」「譲渡費用に過大な請求がある」などと判断されると、確認や調査が入ることがあります。したがって、売買契約書、領収書、登記事項証明書、取得費の明細などをしっかり保管し、求められた際には速やかに提示できるようにしておくべきです。
以下のような表で判断材料を整理しておくと安心です。
譲渡所得20万円以下で申告不要となるかのチェック項目
| 項目 | 該当するか(はい・いいえ) |
| 給与所得のみで年末調整済みか | |
| その他の副業・雑所得はないか | |
| 住民税の申告義務が発生していないか | |
| 控除や特例の適用を希望していないか | |
| 過去に不動産取引で指摘を受けたことがないか |
このように、20万円以下でもすべてのケースで安心というわけではなく、「申告しないリスク」と「申告する手間」のバランスをしっかり見極めたうえで判断を下すことが肝心です。
税務署の判断とグレーゾーン事例
相続不動産の売却に関する確定申告の要否については、税法上のルールだけでなく、税務署の運用方針や判断にも左右されることがあります。特に「グレーゾーン」と呼ばれる事例では、表面的には申告が不要に見えても、後日税務署から問い合わせや調査が入るケースがあるため注意が必要です。
たとえば、以下のようなケースはグレーゾーンに該当しやすいです。
- 複数人の相続人で共有している不動産を売却した場合
- 相続登記が未完了のまま売却した場合
- 売却価格が不自然に安い、あるいは親族間での売却など特別な事情がある場合
- 譲渡費用として認められない支出を経費として計上している場合
- 取得費の証明書類が一切残っていない場合
このような場合、確定申告を行わなかったとしても、税務署が後から「申告漏れ」と判断することがあります。特に「相続人間での協議内容が明確でない」「売買契約書に不備がある」「申告書の添付資料が不足している」といった状況では、疑義を持たれやすくなります。
税務署の立場としては、「納税者が正確に理解している前提」でルールを運用しています。そのため、「知らなかった」「手続きが複雑だった」といった理由は通用しないケースがほとんどです。無申告加算税や延滞税の対象になる前に、可能な限り情報を整理し、判断に迷った場合は税理士や税務署に相談することが推奨されます。
さらに、最近では不動産取引データが電子化されており、登記や売買契約、相続登記などの情報は各機関で連携されています。これにより、「売却事実が税務署にバレない」ということはほぼなくなっており、申告漏れは高い確率で把握されるようになっています。
また、相続財産に対しては相続税の申告時に財産評価明細書や遺産分割協議書を提出するため、それらの書類と売却後の状況に整合性がないと判断されれば、追加調査の対象になることもあります。
判断が難しいときの基本的な対処法は以下のとおりです。
- 国税庁の公式サイトや相談窓口を活用する
- 地元の税務署に事前相談をする(面談・電話・メール対応あり)
- 税理士の無料相談を活用する(地域によっては商工会などで実施)
これらの相談先は公的に運営されており、一定の中立性と信頼性があります。情報の真偽が不安なときは、まずこうした第三者機関を利用することで、安全な判断が可能になります。閲覧者自身が「確定申告が不要か否か」を独断で決めてしまわず、判断材料と相談先をしっかり確保しておく姿勢が求められます。
相続不動産売却に必要な確定申告書類一覧と準備方法
申告に必要な書類一覧
相続した不動産を売却し、その譲渡益について確定申告が必要になった場合、適切な書類を事前に準備しておくことは極めて重要です。手続きの煩雑さを避けるためにも、以下のような申告関連書類を網羅的に把握しておくことが、確定申告のスムーズな進行に直結します。
以下は、相続不動産売却時の確定申告で必要とされる主な書類を一覧化したものです。
| 書類名称 | 内容 | 入手元 | 備考 |
| 確定申告書B様式 | 所得税の申告に使用 | 国税庁サイトまたは税務署 | e-Taxでも作成可 |
| 譲渡所得の内訳書 | 不動産の売却益計算用 | 国税庁サイトまたは税務署 | 売却金額や取得費を記載 |
| 売買契約書(写し) | 売却金額の証明 | 不動産会社 | 契約締結時に受領 |
| 登記事項証明書 | 所有権や売却不動産の確認 | 法務局 | 最新版が必要 |
| 取得費関連資料 | 被相続人が購入時の契約書や領収書等 | 被相続人の保管資料等 | 不明な場合は概算可 |
| 相続時の登記関係書類 | 相続人の所有を証明 | 法務局 | 相続登記完了後に発行可 |
| 相続関係説明図 | 相続人の関係を整理 | 自作または司法書士に依頼 | 相続登記で利用 |
| 相続税申告書の写し | 相続税との整合性確認 | 相続税申告時に作成 | 相続税申告をした場合のみ |
| 固定資産税評価証明書 | 不動産の評価額を確認 | 市区町村役場 | 課税明細書でも代用可 |
| マイナンバーカードの写し | 本人確認用 | 本人 | 通知カードでも可 |
| 本人確認書類(運転免許証等) | 申告者本人確認用 | 本人 | コピー可 |
こうした書類が揃っていれば、譲渡所得の計算から確定申告書の作成、税務署への提出までの一連の流れが非常にスムーズになります。特に「譲渡所得の内訳書」と「売買契約書」は、正確な譲渡所得計算に不可欠です。
さらに注意したいのは、相続不動産売却時に「3000万円特別控除」などの特例を適用するケースです。この場合には、以下の追加書類が必要となります。
| 特例適用時の追加書類 | 用途 |
| 居住用財産の譲渡特例に関する証明書 | 3000万円特別控除の適用確認 |
| 同居の証明書類(住民票など) | 被相続人が居住していたことの証明 |
| 空き家であったことの証明資料 | 居住実態がない場合に備える |
これらを取り漏れると特例が適用されず、多額の税金が発生するリスクがあるため、書類の種類・提出条件をしっかり確認しましょう。
特にe-Taxを活用する場合には、電子データとしてスキャンした書類の提出が求められることがあるため、紙とデジタルの両方での管理体制を整えておくと安心です。
書類がないときの代替手段
相続不動産の売却にともなう確定申告では、多数の書類が求められますが、現実には「必要書類が見つからない」「被相続人が保管していなかった」といったケースも少なくありません。そうした状況に直面したとき、どのように対応すべきか、現実的な代替手段を明確に知っておくことが極めて重要です。
書類が紛失・未入手であっても、完全に申告ができなくなるわけではありません。国税庁や税務署も「可能な範囲での推定や代替資料による証明」を容認しているため、状況に応じた対応が必要となります。
以下に、主な紛失時の対応例と代替手段をまとめた一覧表を提示します。
| 紛失した書類 | 代替手段 | 補足情報 |
| 取得費に関する契約書や領収書 | 不動産業者からの売買履歴の取得、概算取得費(売却額の5%)の適用 | 概算は税額が高くなる傾向 |
| 登記事項証明書 | 法務局で再発行 | ネット申請も可能(登記情報提供サービス) |
| 相続登記書類 | 登記済証(権利証)や登記識別情報の再取得 | 登記内容確認後、再発行手続き |
| 固定資産税評価証明書 | 課税明細書、納税通知書 | 最新年度分のコピーを市役所で取得可能 |
| 売買契約書 | 仲介業者への再発行依頼 | 売却時の不動産会社が保管していることが多い |
| 相続税申告書控え | 税理士、または管轄税務署への写し請求 | 過去の申告データが残っている場合あり |
特に取得費の証明に関するトラブルは頻出です。取得費が証明できない場合、「概算取得費」として売却額の5%を取得費とみなすことができますが、本来の取得費が高い場合と比べて納税額が大きくなりやすいため、注意が必要です。
また、以下のようなケースでは「特例適用書類の代替措置」も検討されます。
- 被相続人が居住していた証明が難しい場合 → 電気・ガス・水道の請求書などで居住実態を示す
- 空き家特例の証明書類がない場合 → 住民票の除票や固定資産台帳の写しなどで代用
このように、確定申告に必要な書類が手元にない場合でも、他の資料や代替措置を用いることで申告を完結させることが可能です。ただし、代替書類の有効性や提出可否については、税務署に事前確認を取るのが賢明です。
さらに、書類再取得の際に発生する「取得手数料」「郵送費」「時間的コスト」も想定しておくと、より現実的なスケジューリングが可能となります。
このように、書類が不足していても「取れる手段は多数ある」ことを知っておくことが、申告準備において最大の安心材料となります。
書類の入手先・所要時間・注意点
相続不動産の売却によって譲渡所得が発生した場合、確定申告を行うためには多数の書類を揃える必要があります。しかし、「どこで入手するのか」「どれくらい時間がかかるのか」「どう注意すべきか」といった情報があいまいなままでは、申告準備に無駄な手間や遅延が生じてしまいます。
まず、以下に申告に必要な代表的書類とその取得先、目安となる取得時間、注意点を表にまとめます。
| 書類名 | 入手先 | 所要時間(目安) | 注意点 |
| 登記事項証明書 | 法務局 | 即日(窓口)または数日(郵送) | 所在地が他県の場合はオンライン推奨 |
| 固定資産税評価証明書 | 不動産所在地の市区町村役所 | 即日~3日程度 | 所有者と申請者が異なる場合、委任状が必要 |
| 相続関係説明図 | 自作または司法書士に依頼 | 数日~1週間 | 正確な戸籍情報が必要、間違いが多い |
| 戸籍謄本・住民票・除票 | 本籍地の役所 | 即日 | 被相続人の死亡から現在までの連続性が重要 |
| 取得費関係の領収書・売買契約書 | 保管書類または不動産会社へ依頼 | 1日~1週間 | 紛失時は概算取得費扱いになる可能性あり |
| 譲渡に関する売買契約書 | 売却時の不動産会社 | 1日~1週間 | 印紙税の納付印の有無にも注意 |
| 仲介手数料の領収書 | 仲介業者 | 即日~数日 | 控除対象として有効、忘れがち |
| マイナンバーカードまたは通知カードの写し | 自己保管 | 即日 | 提出時には本人確認書類も同封すること |
| 確定申告書B様式・第三表・計算明細書 | 国税庁ウェブサイトまたは税務署 | 即時ダウンロード可 | 書き方は税理士または窓口で相談可能 |
申告に必要な書類のなかには「誰が取得できるか」が限定されているものがあります。たとえば、戸籍や住民票は「法定相続人」に限られることが多く、第三者が代理取得するには委任状が必要です。
書類の準備にあたっては以下の注意点も忘れずに押さえておきましょう。
書類準備時の重要な注意点リスト
- 書類の記載内容は一致しているか(登記簿と住民票の地番表記など)
- 証明書の有効期限に注意(住民票や印鑑証明書は発行後3カ月以内が原則)
- 提出用と控え用を両方準備すること
- 原本提出が求められるか、コピーでよいかを確認
- 書類の送付時は追跡可能な方法を選ぶ(書留、レターパック等)
また、申告に関して不安がある場合や、自分での準備が難しいと感じた場合には、相続や譲渡所得に強い税理士への相談も一つの選択肢です。税理士報酬は内容により異なりますが、確定申告のみであれば5万円~10万円前後が相場です。
加えて、地域ごとに異なる書類名・取得方法が存在するケースもあるため、東京都・神奈川県・大阪市などの主要自治体の公式HPを確認することも有効です。
以上の情報を踏まえ、早期かつ確実な書類準備を行えば、確定申告の煩雑さを大きく軽減できます。
まとめ
相続した不動産を売却する際、確定申告が必ずしも必要ではないケースが存在します。特に譲渡所得がマイナスになった場合や、年間の所得合計が一定額を下回る場合は、申告義務が発生しないこともあります。ただし、その判断には正確な知識が求められ、自己判断での放置はリスクが伴います。
また、確定申告が不要となるためには、取得費や譲渡費用の適正な計算、相続人間の遺産分割の明確化、そして3000万円特別控除の適用可否など、複数の条件が絡み合います。たとえば、相続から3年以内の売却かつ一定の条件を満たすことで、控除を適用して申告不要となるケースもある一方で、書類の不備や認識違いで後から税務署に指摘される例も少なくありません。
「自分のケースは該当するのか分からない」「必要書類が揃っていない」という声も多く聞かれます。特に書類が見つからない場合は、代替資料の提出や概算での処理が可能な場合もあるため、早めの準備と専門家への相談が推奨されます。
この記事では、税務署や国税庁の公開資料をもとに、確定申告が不要になる具体的な条件と判断ポイントをわかりやすく整理しました。無申告加算税や延滞税などの損失を未然に防ぐためにも、正しい情報に基づいた対応が何より重要です。
不安を感じたまま放置せず、一つひとつの条件と向き合いながら、自身にとって最適な対応策を選ぶことが、金銭的損失を回避する最大の鍵となります。
株式会社トップトラストは、不動産の購入、管理、税務相談、売却など幅広いサービスをご提供しています。お客様のニーズに応じた最適な不動産プランをご提案し、安心・安全な取引をサポートいたします。また、経験豊富なスタッフが税務や法務に関するご相談にも対応し、お客様の大切な資産を守るためのアドバイスを行っています。不動産に関するあらゆるご要望にお応えし、お客様の夢を実現するお手伝いをいたします。

| 株式会社トップトラスト | |
|---|---|
| 住所 | 〒160-0007東京都新宿区荒木町5番地 四谷荒木町スクエア5F・6F |
| 電話 | 03-5315-0370 |
よくある質問
Q. 相続した家を売却して利益が出なかった場合、本当に確定申告は不要なのですか?
A. 譲渡所得がマイナス、つまり不動産を売却しても取得費や譲渡費用の合計が売却価格を上回る場合は、所得税や住民税が課税されず、確定申告も原則不要となります。特に昭和の時代に建てられた建物は減価償却により取得価額が低くなりやすいため、利益が出づらい傾向があります。ただし、損益通算を行いたい場合や翌年以降の節税に活用したい場合は、申告しておくメリットがあります。
Q. 税務署に確定申告不要と判断されなかった場合、どのようなペナルティがありますか?
A. 本来申告すべき所得を無申告のまま放置してしまうと、無申告加算税が15%、さらに延滞税が年利7.3%を上限に加算されるケースがあります。また、税務署からの調査が入ると、過去5年分さかのぼって申告義務が問われる可能性もあります。特に相続不動産の売却では「控除適用の条件を満たしていないのに申告しなかった」ケースでペナルティが発生しやすいため、自己判断には十分注意が必要です。
Q. 必要書類を紛失してしまった場合、どうやって取得費や譲渡費用を証明すれば良いですか?
A. 建物の取得費が不明な場合、固定資産税評価額の1.0倍〜1.2倍で概算計算する方法があります。また、リフォーム工事の領収書や登記事項証明書、売買契約書の写しなどから間接的に算出することも可能です。古い資料がない場合でも、不動産会社や市区町村の役所に問い合わせれば再発行できる書類も多く、時間をかければおおよその取得費は算出できます。取得費がゼロとみなされると、全額が課税対象になる恐れがあるため、できる限り客観的資料で証明する努力が重要です。
会社概要
会社名・・・株式会社トップトラスト
所在地・・・〒160-0007 東京都新宿区荒木町5番地四谷荒木町スクエア5F・6F
電話番号・・・03-5315-0370